

- EduTown SDGs
- SDGs取組事例
- 服のチカラで世界を笑顔に
毎日学校に着ていく服、部活やスポーツクラブのユニフォーム、寒さをしのぐコートなど、わたしたちは毎日いろいろな服を着て暮らしています。そして、お気に入りの服はわたしたちに元気を与えてくれます。
しかし、着られなくなった服、要らなくなった服はどうしているでしょうか。
「ユニクロ」「ジーユー」などのブランドを世界中で展開するファーストリテイリングは、良い服をつくり、より良い社会をつくることに取り組んでいます。ファーストリテイリングの中野友華さんに、服をつくる責任とつかう責任について教えてもらいました。
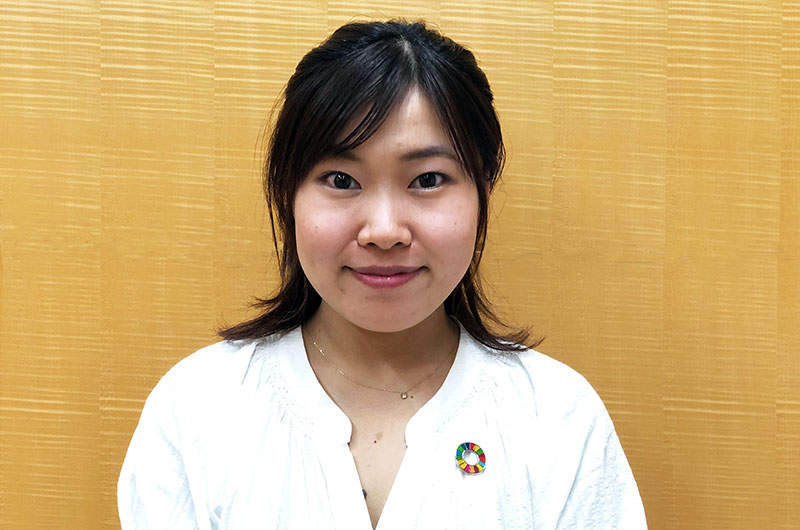
株式会社ファーストリテイリング サステナビリティ部 ビジネス・社会課題解決連動チーム 中野友華さん
長く使うことができる服づくり
わたしたちは、季節や流行、目的に合わせて毎日服を選び、着て生活をしていますよね。さまざまな服を選んで着こなすことはとても楽しいですが、タンスの中で眠っている服や、捨てられてしまう服もあります。
服が破れたり汚れたりして着られなくなったというだけではなく、サイズが合わなくなってしまった、流行が過ぎてしまった、新しい服が欲しくなったなどといった理由で、まだ着られるのにもかかわらずに捨てられてしまう服もあります。(中野さん)
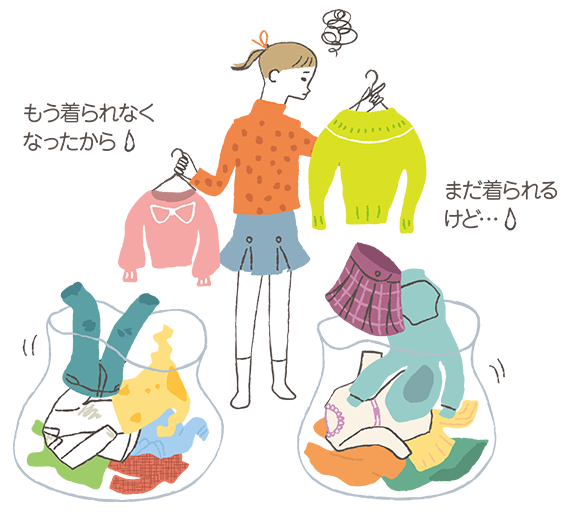
服が着られなくなったり、要らなくなったりする理由はさまざまですが、少しでも長く服を大切に使ってもらうために、ファーストリテイリングはどのようなことに取り組んでいるのでしょうか。
ムダなものをつくらないこと、そして売らないこと。「質がよく、長持ちする」を服づくりのコンセプトにしています。世の中の人たちの生活に必要な服、欲しいと思っている服をしっかりと理解し、完成度の高い商品づくりを目指しています。(中野さん)

「ムダなものはつくらない、売らない」という考えのもと、質の高い服づくりに取り組んでいる。
(写真左:「ユニクロ WOMENパフテックジャケット (2024)」、写真右:「ジーユー ヘビーウェイトスウェットフルジップパーカ(ユニセックス)(2024)」)
環境にも人にもやさしい服づくりを目指して
ファーストリテイリングがつくる服は1年間で十数億枚。 とてもたくさんの服をつくる会社として、ほかにも気を付けていることがあると中野さんは言います。
服にはコットン(綿花)やウール(羊の毛)などの原材料が必要で、服をつくる工場などでは水や電気などを使います。だからこそ、わたしたちは限りある資源を有効に使い、服をつくる過程で水や電気をなるべくムダにしないなど、環境のことを考えた服づくりにも取り組んでいます。商品に含まれる化学物質削減の取り組みもその一環です。
また、リサイクル素材を活用した服の開発、回収したダウン商品から取り出したダウンを素材の一部に使用したリサイクルダウンの開発なども行っています。

お客様のご不用になったユニクロのダウン商品を回収し、ダウンとフェザーのリサイクルを進めています。東レと共同で開発した新しいテクノロジーで、効率的に、リサイクル素材を作り出し、洗浄。新たなダウン商品に生まれ変わらせています。
一枚の服ができるまでには、原材料を生産する農家で働く人、工場で生地の加工や縫製をする人など、たくさんの人が関わります。こうした人たちがやりがいを持って、いきいきと働けなければ、良い服をつくることはできません。
そこで、取引先の工場で働く人を対象に、労働時間の管理や賃金の支払いなどについて、定期的に評価する仕組みをつくり、労働環境の改善に取り組んでいます。また、取引先の工場における人権と労働環境に関する問題を素早く確認して、解決するために、取引先工場の従業員が直接、ファーストリテイリングに相談できるホットラインを設置しています。
服づくりに関わる人の権利を尊重し、安心して健康に働ける環境づくりに取り組むことは、良い服に欠かせない最も大切なことの一つです。(中野さん)

工場で働く人が生き生きと働ける環境をつくることが、よい服づくりにもつながります。
ファーストリテイリングでは、質が高く長く使え、資源や環境、働く人のことも考えた「良い服」をつくることに取り組んでいますが、服をつくる会社として、ほかにも取り組んでいることがあります。
着なくなった服で世界を元気に
まだ着られるのに捨てられてしまう服がある一方で、世界には必要な服が足りない人たちがいます。
ファーストリテイリングでは、ユニクロやジーユーのお店で、着なくなった服を回収し、難民などの服を必要としている人たちに届けるほか、資源として有効活用するため、全商品を対象にしたリサイクル活動に取り組んでいます。この活動には、わたしたちも参加することができます。

ユニクロやジーユーのお店で回収した服を、着られるものと着られないものに仕分け、寄贈するものは、季節、サイズなどで分類し、現地のニーズに合わせて届けています。
難民の中には、寒さや暑さから体を守るための最低限の服さえ足りていない人たちや、同じ服をボロボロになるまで着続けている人がいます。こうした人たちにとって、支援物資として服が届くのはとてもうれしいことです。
わたしたちは、みなさんがユニクロやジーユーのお店のリサイクルボックスに入れた服を、世界の難民を支援する国連機関、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)や各地のNGOと協力して、難民の人に支援物資として届けています。
何かの理由で不要になった服でも、だれかのためになるようにリサイクル・リユースをして、服の持つ力を最後まで最大限に活かすこと。それも服をつくる会社の責任だと思い、この活動に取り組んでいます。(中野さん)

難民の人たちの表情がぱっと明るくなってうれしそうにしている子どもたちやお母さんたちの姿を見ると、大きなはげみになると中野さんは言います。
2001年にユニクロのフリース商品の回収から始まった取り組みは、2006年にはフリース以外も含む全商品を、2010年からはジーユーの商品にも回収範囲を広げ、2024年までに81の国と地域に5,897万点の服を届けています。

ユニクロやジーユーのお店にある回収ボックス。要らなくなった服を持ちこむだけでだれもが参加できる。
"届けよう、服のチカラ"プロジェクト
服のリサイクル活動には、小学校、中学校、高校のみなさんだからこそできることがあります。
難民のおよそ半数は、18歳未満のみなさんと同じくらいの年齢の子どもたちで、子ども用の服は特に不足しています。そこで、わたしたちは、日本の学校のみなさんと協力し、学校で回収した子ども服を難民の子どもたちに届ける「"届けよう、服のチカラ"プロジェクト」を始めました。(中野さん)
"届けよう、服のチカラ"プロジェクト
1.学ぶ・知る
「服のチカラ」についてユニクロやジーユーの社員による授業で学びます。

2.考える・呼びかける
子どもたちが中心になってオリジナルポスターを作成するなど、服を集める方法を考えて校内や地域に呼びかけます。

3.回収・発送する
手作りの回収ボックスを作成するなど、工夫をして回収した服は子どもたちで梱包し、倉庫へ発送します。

4.届ける・報告
集めた服が難民の子どもたちに届けられます。

このプロジェクトは、みなさんが主役となって、身の回りの着なくなった子ども服を集め、それを難民の子どもたちに届けるプロジェクトです。2013年のスタートからこれまで4,315校、のべ47万人の子どもたちが参加しました。みなさんが集めた服は、わたしたちが責任を持って届けますので、ぜひ参加してもらいたいですね。(中野さん)
服のチカラを、社会のチカラに
服は、人が生きていくために必要なものであるだけではなく、人を幸せにする、笑顔にするチカラがあります。だからこそ、わたしたちは、服を着る喜びや楽しさを一人でも多くの人に伝えたいと思っています。そのために、より良い服をより良い方法でつくり、服を必要としているあらゆる人たちに届ける取り組みに力を入れています。(中野さん)

服を着る、「つかう責任」として、わたしたちには何ができるでしょうか。
服を選ぶときには、それが本当に必要なものかどうかをしっかりと考えて、必要な分だけムダなくそろえて、できるだけ長く大切に使ってほしいですね。それでも、身の回りに着られなくなった服があるなら、それを必要としているほかの人にあげたり、リサイクルしたりするなど、ただゴミとして捨てるのではない方法を考えてほしいと思います。
もちろん、「全商品リサイクル活動」や「"届けよう、服のチカラ"プロジェクト」などに参加してみることも、みなさんの行動で世界をより良くするためにできることの一つの方法です。
より良い社会をつくるために自分たちに行動できることを考えて、どんどんチャレンジしてみてください。(中野さん)
原稿作成:株式会社 日経BP
仕事人インタビュー
この記事に関連する目標
関連記事
-
みんなで取り組むペットボトルの完全循環
株式会社セブン&アイ・ホールディングス
-
プラスチックごみの問題に取り組み、みんなが考えるきっかけに
ネスレ日本株式会社
-
健康で強い体、元気な体をつくる
味の素株式会社
-
きれいな水を使い続けていくためにできること
サントリーホールディングス株式会社
-
持続可能な未来を支える再生可能エネルギー
いちごECOエナジー株式会社
-
半導体をテストで支えて持続可能な社会をつくる
株式会社アドバンテスト
-
いつまでも安心して住み続けられるまちをつくる
積水化学工業株式会社
-
二酸化炭素を減らしてクリーンな空の旅を
日本航空株式会社
-
世界中にクリーンなクルマを
トヨタ自動車株式会社
-
だれもが安心して移動できるまちを
トヨタ自動車株式会社
-
木を育て、使い、森林の循環をつくる
住友林業株式会社
おすすめの記事
-
木を育て、使い、森林の循環をつくる
住友林業株式会社
-
半導体をテストで支えて持続可能な社会をつくる
株式会社アドバンテスト
-
みんなで取り組むペットボトルの完全循環
株式会社セブン&アイ・ホールディングス
-
きれいな水を使い続けていくためにできること
サントリーホールディングス株式会社
-
健康で強い体、元気な体をつくる
味の素株式会社
-
いつまでも安心して住み続けられるまちをつくる
積水化学工業株式会社
-
持続可能な未来を支える再生可能エネルギー
いちごECOエナジー株式会社
-
二酸化炭素を減らしてクリーンな空の旅を
日本航空株式会社
-
世界中にクリーンなクルマを
トヨタ自動車株式会社
-
だれもが安心して移動できるまちを
トヨタ自動車株式会社
-
服のチカラで世界を笑顔に
株式会社ファーストリテイリング(ユニクロ・ジーユー)
-
プラスチックごみの問題に取り組み、みんなが考えるきっかけに
ネスレ日本株式会社








